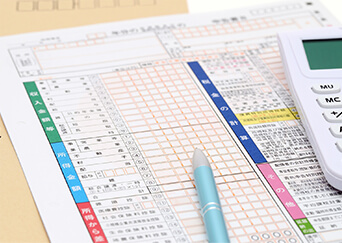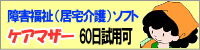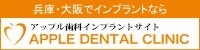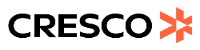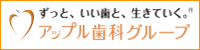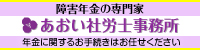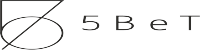ストーリー
知っていますか?意外と身近な障害者と私たち
優先席・車イスマークなど、障害のある方に配慮した施設や設備を目にすることはありませんか?
意外と知られていない障害を抱える人の現状と、
日本と日本障害者リハビリテーション協会が抱える課題をご紹介致します。
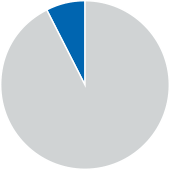
日本国民のおよそ
7.4%
が何らかの障害を有しています
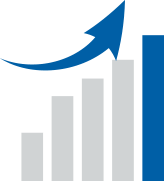
身体障害者数は
昭和45年に比べ
約3倍
に増加。いまだ増加傾向にあります
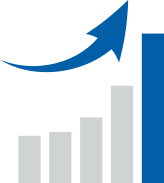
知的障害者数は
平成7年に比べ
約3.2倍
に増加。いまだ増加傾向にあります
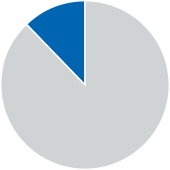
障害のある人に
遭遇しても
12%
の人がどのように接し
たらよいかわからない
と回答しています
(内閣府調査より)
今、リハビリテーションの
必要性が高まっています。

日本人の7.4%は何らかの障害を抱え、私たちと同じように生活を送っています。あなたの知っている家族・友人の100人のうち7.4人は障害を抱えている計算になります。
家族・友人の誰か大切な人が障害を持っていたら、
障害を抱えてしまったら、
あなたはどんなことをしたいと思いますか。
日本障害者リハビリテーション協会では、国内外における障害者のリハビリテーションに関する調査研究を行うとともに、国際リハビリテーション協会の加盟団体として国際的連携を強化し、障害者のリハビリテーション事業の振興に寄与します。
リハビリテーション体験談

人生の勝負は車椅子に乗ってからスタート
イニシャル:M.Y
中学1、2年生の時、約310日の間、家から遠く離れた大学病院に入院し、歩行のためのリハビリを受けた。
小学4年生の時、脊髄腫瘍があることが分かり、小学卒業の頃から背中の痛み、足のもつれが始まり、14歳の朝、ベッドから起き上がれなくなってしまった。
急遽、入院し腫瘍を摘出する手術を受けたが、麻酔から目が覚めた時には「足がある」という感覚はなく、動かそうとしても力の入れ方が分からなかった。
当時は医師や両親から病気について知らされておらず、自分の体に何が起きているのか、この先、どうなっていくのか全く知らず、中学に戻ること、元通り歩ける、走れることを信じて疑わなかった。
ある程度、手術の傷が良くなるとリハビリが始まった。最初は両足に装具をはめ、無理やり膝を伸ばした状態で固定し、平行棒の間に立つことから始まった。とは言っても足の感覚と筋力はゼロなので、立っているという意識はなく、倒れないように両腕で全体重を支えているのに必死だった。
朝と夕方の1日2回、トータル4時間をリハビリ室で過ごした。1か月くらい経つと平行棒の間を5往復、腕で歩くことができるようになったが元のようには程遠く、だんだんとリハビリへの意欲がなくなり、付き添っていた祖母に悪態をついたり、両親にリハビリをしても意味がないと言うようになった。
特に周りから言われる「頑張れ」という言葉が反発したくなり、その言葉を聞くのが一番辛かった。普通、「頑張れ」という言葉は元気づけたり、励ましたり、応援したりするなど、言われた方はパワーをもらう言葉である。
しかし当時は「頑張れ」と言われると、「これだけ歩く訓練をしているのに、まだ頑張らなければいけないのか、頑張っていないようにみえるのか」と思い、腹立たしさを感じると共に、応援に応えられない自分が情けなかった。
リハビリテーションの基本的な意味は「元の適した状態に戻すこと」であり、自分の場合は「歩けるようになること」であった。そのために学校を休み入院生活を送ったが、1年を過ぎても歩行機能は改善せず、1年半を超えた頃からは、いつリハビリが終わりになるのかと疑問を持ち始めた。
もし歩けるようになるまで続くのであれば、一生リハビリをしなければいけないのかと本気で考えたこともあった。リハビリを否定するつもりはなく、必要な人、リハビリによって生活しやすくなった人がほとんどであると思う。
あきらめずに頑張り続ける人がいることも十分理解しているつもりである。しかし間違ってはいけないことは、「障害はあってはいけない、健常者に少しでも近づかなければいけない」という考えは正しくないということである。
そして何より大事なことは、本人自身の意思最大限に尊重することだと思う。14歳だったあの時、親や医師は自分には体の状況や障害のことを教えてくれなかった。
中学生には酷な話で、聞けばショックを受けるだろうと心配したからだと、大人になってから聞いたが話して欲しかったと思うことがある。実際に、車椅子生活になると知った時、うまく言えないが自分自身はほっとした。
人生の勝負は車椅子に乗ってからスタートすると思った。医師や家族を恨んではいないが、しかし、あの時、自分を信頼して伝えてくれていたら、また共感してくれる人が傍にいてくれたら、堂々とスタートを切れたと思う。
自分が経験したリハビリテーションは、辛い思い出であるが、多くの人との出会いがあり、様々な障害者とつながることができた。そして何より、障害者とは何者かということを考える貴重なきっかけであり、今の自分を価値観に大きな影響を与えるものだった。
寄付者の声
日本障害者リハビリテーション協会に寄付してくださった寄付者の声をご紹介致します。
「僕の大切な人が事故で障害を持つこととなってしまいました。少しでもお役に立てればと思い、少額ですが、寄付させていただきます。こういった団体があることを、そもそも知りませんでした。検索して初めて知りました。」
「僕自身精神障がい者でして、このような協会を支えていけること有難いです。」
支援事業
日本障害者リハビリテーション協会では、すべての障害における次の支援活動を行なっています。
ご寄付の対象事業を指定することもできます。ご寄付の際にお知らせください。

リハビリテーションに関する調査研究・広報
総合リハビリテーション研究大会の開催や、緊急災害時に障害者を支援する情報システムの研究など、学術的な面からリハビリテーションを支えています。

国際シンボルマーク(車いすマーク)の普及・使用の管理
当協会は日本における国際シンボルマーク(車いすマーク)の使用管理を委ねられており、正しい理解と普及に努めています。

日本国内での障害者団体等への協力
日本障害フォーラム(JDF)、日本障害者協議会、障害者放送協議会に参加し、各種活動を支援しています。

障害者支援分野での国際協力
約100の国と地域、約700団体が加盟している国際リハビリテーション協会(RI)への参加、アジア太平洋障害フォーラムへの支援など、国際協力を進めています。

海外の障害者に対する人材育成事業
開発途上国から毎年障害者を受け入れ、研修を実施しています。「障害者権利条約の実践のための障害者リーダー能力強化」コースと「ダスキン・アジア太平洋障害者リーダー育成事業」があります。

地域に根ざした共生社会の実現(CBID)への取組
障害のある人をはじめとする、グループを含めて誰一人取り残されないような地域社会をつくるため、国内外で取組を進めています。

ICT技術を活用した障害者支援
障害保健福祉研究情報システム事業(DINF)や障害者情報ネットワーク(ノーマネット)、デジタル録音図書の国際標準規格であるDAISYの開発等を通して支援を広げています。

DAISY図書(デジタル図書)の研究開発・普及
ディスレクシア等の発達障害、視覚障害、その他障害のある方のために、世界的な規格でのマルチメディアDAISY図書の研究開発、ならびに普及を行っています。

全国障害者総合福祉センターの運営
全国障害者総合福祉センター (戸山サンライズ)を運営し、相談事業、研修事業、情報提供・啓発事業、災害用緊急情報・備蓄物資の保管事業などを行っています。
本協会へのサポーター・協力会社・団体です。
※掲載したバナー広告に起因する名誉毀損、プライバシーの侵害、著作権の侵害、その他を理由とする賠償請求やその他の請求に関して、本協会は一切の責任を負いません。バナー広告に関する一切の責任は広告主が負うものとします。