遺贈で第3者に財産を残せる!遺贈での税金や控除について

超高齢化社会に突入する日本では、預貯金や土地、家といった財産をどうしようか悩んでいる人も少なくない実情があります。通常の相続手続きでは、内縁の妻や養子縁組をしていない人などの第3者に、財産を残すことはできません。
これに対して遺贈という仕組みを使うと、法定相続人ではない人にも大事な遺産を与えられることが可能になります。
そこで今回は、高齢化社会により国内での注目度が高まりつつある遺贈について、基本的な知識をわかりやすく解説していきます。
遺贈とはなにか?
遺贈の定義は、遺言によって遺言者の財産を受遺者に無償で譲ることを言います。
遺贈の仕組みを使うと、内縁の夫や妻、法律上の親子関係がない家族の中でも、法定相続人ではない相手に財産を残せます。
また身寄りのいないお年寄りや、生涯独身を貫く人においては、介護で面倒を見てくれた良心的なヘルパーや、ボランティア、親しい友人などに遺贈を通して財産を譲るケースも増加傾向にあるようです。ちなみに子どもの貧困や、子育て問題の課題解決などに取り組むNPO法人の中には、遺贈による寄付を受け付ける団体も意外に多く存在しています。
そのため、財産を残したいと思えるほどの親しい友人知人がいない場合は、遺贈を使いこうした団体へ貯めたお金などを譲るケースもあり、社会の役に立てることも可能な時代になりつつあると考えられているのです。
包括遺贈と特定遺贈の違いとは?
遺贈には、与える財産の割合を指定する「包括遺贈」と、財産の金額や内容を具体的に指定する「特定遺贈」の2種類があります。
「全財産の2分の1を内縁の妻に与える」といった内容で遺言指定のできる包括遺贈には、遺贈者の生前に生じる預貯金の増減や不動産処分などの財産構成の変化に対して、柔軟な対応をおこなえる利点があります。
一方で、法定相続人と同じように権利と義務を負う包括遺贈の場合、遺贈者に借金や債務などのマイナス財産があったときに、それらも引き継がなければならないデメリットが生じるケースもあるのです。
これに対して、無償で譲り受ける財産の種類や内容を具体的に指定できる特定遺贈の場合、包括遺贈の弱点とも言えるマイナス財産があったときに、他の相続人との揉め事が起こりにくい特徴があります。
しかしながら特定遺贈の目的で遺言書を作った場合、財産構成の変化に対応できるように定期的な見直しやチェックをおこなう必要があります。このようにそれぞれにメリット・デメリットのある遺贈の種類は、残したい財産の内容や受遺者となる相手などとの話し合いを踏まえて、残された側に負担のかからない手段を選ぶ必要があると捉えてください。
遺贈を受ける場合に気をつけたい税金のこと
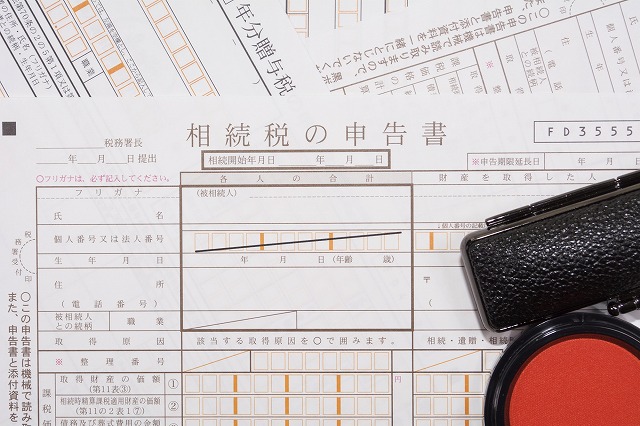
遺贈によって財産を譲るときには、受遺者側にも注意すべき税制上のポイントが多くあります。
控除額の計算人数には含まず、税額割り振りには含める
まず、法定相続人ではない第3者に財産の遺贈をするときには、この人を相続税計算における基礎控除額の計算人数に含めることはありません。
しかしながら、相続財産の取得割合に応じた税金の振り分けをする際には、法定相続人から見て第3者となる受遺者も含めて税額を決定する仕組みとなるため、注意が必要です。
相続税が2割増になる
遺贈で残された財産も、相続税の対象です。
そのため、法定相続人ではない第3者が遺贈を受けた場合、相続税が通常の20%アップになってしまうことも頭に入れておく必要があります。ちなみにこの2割加算は、相続人ではないお孫さんなどへの遺贈でも適用されます。したがって、相続もしくは遺贈を使って効率よく財産を譲る方法を考えるときに、税金への対策という目的があるときには特に注意をしてください。
亡くなるまでの3年分の贈与は課税対象
遺贈者の相続開始日から3年遡った期間内に生前贈与された財産は、相続税の課税対象となります。
したがってこの条件に合う遺贈をしているときには、相続をする財産にプラスして税額計算をしなければなりません。しかしながら、受遺者が既に贈与税を納めていた場合、相続税額から贈与税額を差し引ける贈与税額控除の制度が使える形となります。
遺贈における控除とは?
遺贈で財産を受けとる場合も、次の計算式で求める基礎控除分を課税対象額から差し引くことができます。
・基礎控除 = 3,000万円+600万円×相続人の人数
そのため例えば、法定相続人が3人いる遺贈者の財産総額が3,000万円だった場合は、上記の計算式で求めた基礎控除額の4,800万円(3,000万円+3人×600万円)に満たないという理由で、遺贈と相続どちらを使っていても相続税はかかりません。
しかし、先ほどご紹介したとおり遺贈による財産の取得には、相続税の2割加算などの規定もありますので、節税目的で控除などを気にされるときには、専門家に相談をしながら慎重に遺言書の作成など進めるのが理想的となるでしょう。
遺言次第で誰にでも財産を残すことができる
相続人だけでなく誰にでも財産を残せる遺贈には、負の財産を譲り渡すことにより、家族の間でトラブルが発生しやすい側面もあります。そのため、この仕組みを使って財産を譲る際には、遺贈者だけでなく受遺者側でも相続税を中心とした法律知識をきちんと確認し、最適な方法で慎重に手続きなどを進めるようにしてください。